「何かを真剣にやってきた事はあったのだろうか?」
「壁にぶちあたった事はあったのだろうか?」
むかつく質問だ。そんな事、深く考えないで気がつけば体ばかり大きくなっていたし、自分というコンピューターでそんなワードを検索してみても、十六年という短い人生の中で思い当たる節は一切見当たらないとの結果が出ていた。気にしている訳じゃない、多分。けれどふとした時にその質問達は、俺の中にずかずかと土足でかつ、我が物顔で入り込んでくる。
「本当に?」
「それで平気?」
「苦しくない?」
……むかつく、むかつく。関係ない、余計なお世話、放っといてくれ! だから俺は全力でそんな質問達に対抗する為、ぶれない自分を保ち続ける事を心に決めていた。
現に今もこうやって
(サンタクロースがトナカイに乗って空からゴキブリか何かをばらまいてくれればいいのに……)と「真剣」や「ぶちあたる」という言葉とはほど遠い、クズ丸出しの発想をしていたのだから。
短編「冬空からの贈り物」
勘違いのないように先に言っておく事にしよう。俺の性格は良くない、いや悪い、むしろひん曲がっている。どこでどう間違えたのか、それともそんな才能が生まれつきあったのか、それは俺にもわからない。ただ今、自分の目の前で起きている光景を見て勝手に脳がそんな信号をキャッチしてしまっているのだから、何とも救いようがない。
今日はクリスマス。街にはイルミネーションとかいうちょっと気取った名前の光の塊がチカチカと発色し、もう何百回と聞いて耳にタコができるようなクリスマスソングのメロディは、聞いている側の気持ちなんて一切関係なくだらだらと外部へ放出され続けている。何ともお気遣いの有り難い事だ。そんな「今日の主役は俺達私達以外には考えられない」と言わんばかりの恋人達を、死んだ魚のような目で眺めている俺にとっても実に有り難い。有り難すぎて溢れでた涙が運河を作ってしまいそうな勢いだ、こんちくしょう。
「はー寒っ」
十二月の寒さはいつだって全力投球だ。俺が着ている服なんかおかまいなしにどんどん中へと進行してくるし、その成果もあってか俺は、手や足を冷蔵庫の中にそのまま突っ込んでいるような擬似体験をしている訳だが、さすがに氷の塊になるのは、今後の人生に支障を来すので体をぶるぶると震わせながら無駄な抵抗を続けていた。
ふと後ろを振り返ってみた。夜空を覆い隠す様なやたらと馬鹿でかいデパートがそびえ立っている。最近同じ系列のデパートが次から次へと増えているがこの建物も例外ではないのだろう。人伝いに聞いた話によるとかなり賑わっているらしい。しかも今日はクリスマスときたもんだ。カップルが多いのも当然という事だろう。
まぁいつまでもそんな事をウジウジ言ってても仕方がない。人間あきらめが肝心だ。今日はたまたま俺には彼女がいなかった、たったそれだけの事。この跡付け感が半端じゃない「たまたま」という言葉が思っていた以上に自分を救ってくれていた事に気付き、そう考えるとなんだか世界はちっぽけだなーなんて何かを悟った気分になってしまう俺は、中々のクズだと自負している。それにそんな自分は意外に嫌いでもなかったりするのだからタチが悪い。
都合のいいように解釈した俺は、とりあえず自分に与えられた最低限の使命のようなものを全うしようとしていた。
目の前から必要以上に体を寄せ合ったカップルがやってくる。これで一体何組目だろう。しかも頭の薄くなった冴えないおやじに、思わず目のやり場に困ってしまう様な丈が短いスカートの女子高生。おいおい大丈夫か? どこの高校かしらないが本当にそのおやじでいいのか? もっとましな奴はいなかったのか? というより確信にせまってしまうとそこに金銭的な何かは発生していないのか?
まぁそんな理由は本人達にしかわからないだろうし俺がとやかく言う問題でもないが、男と女がいちゃいちゃして街中を歩いている事に代わりはない。……ちくしょう、なんとも羨ましいっ! おやじこけろっ! その微妙な段差で足を引っかけてこけてしまえっ!!
俺は無意識にそんな呪いをかけていた。 黒魔術選手権か何かあれば俺は、なかなかいい線までいけるのではないかという想像が一瞬脳裏によぎったが確実に今はそんな状況ではなかった。……落ち着け。むやみに心をみだしては駄目だ。義務だと思って実行すれば俺に出来ないはずがない。よくわからない感情が交差する中、俺は意を決して行動に移すことにした。
カップルが近づいてくる。
あと二歩……
あと一歩……
今だ……
「どうぞー!」
軽快な掛け声と共に俺は……俺は!
——ポケットティッシュを二人に差し出していた。
完璧だ。
こんなにも洗練された無駄のない動きがあっただろうか。ひょっとすると俺にはその道の才能があるのかもしれない。我ながら恐ろしい、この溢れ出す才能が。そうだろ、お前たちもそう思うだろ……なぁ、おやじ。
「ってあれ?」
カップルは俺の事など見向きもせず、楽しそうにデパートの中へと去って行った。
俺は差し出した手の行き場を失ってしまい、感情の向くままティッシュを地面に叩き付けていた。
「何でじゃー!」
はぁはぁ……心なしか体が温かくなった様な気がする。気がつくと周りにいた通行人に何かの犯人を見る様な冷たい視線を向けられていた。
俺は「何見てやがる見せもんじゃねぇぞ!」という気持ちを飲み込み、愛想良く会釈をして見せた。
我ながらなんて大人な対応なんだと感心していると、しばらくして小学生ぐらいの男の子と母親がやってきた。楽しそうに会話をして何とも微笑ましい光景だ。男の子は今からクリスマスプレゼントでも買ってもらうのだろう。しかし親子よ、その前に日常生活でここぞという時に役に立つこのブツが必要ではないか。必要だろう必要に違いない。俺は獲物を狙うハンターのように精神を集中する。
あと二歩……
あと一歩……
今だ……
「どうぞ……ぐはっ!」
手を差し伸べると同時にローキックをくらった。そして……
「母ちゃんこのサンタやっちまっていい?」
「健太、駄目よ止めなさい」
男の子……いやクソガキは俺が抵抗しないのを良い事にボコボコと攻撃してくる。地味に痛い。てか母親止める気ないだろ。
「おい、プレゼントだせよ!」
それにしてもなんて口の悪いクソガキだ、この母親は一体どんな教育をしてるんだ全く。将来はカツアゲの常習犯にでもなるであろうクソガキを睨みつけながら俺の脳内で緊急会議が行われた。「こんなガキには現実の厳しさをとことん教えるべきだ! だから全然キレてもオッケーだぜ!」という欲望丸出しの悪の俺と「それは駄目だよ。どこで誰が見てるかもわからないし今、キレたらせっかくのバイト代がなしになるかもしれないよ。だから耐えるんだ」という冷静な善の俺。話し合いの結果、いつの間にやら善の俺が勝利していた。耐えろとの命令だ。
そうだここでキレたら全てが終わる。ただでさえ金欠なのにこんな事で給料がもらえないのは辛い。子供の攻撃ぐらい軽いもんだ、その内飽きて諦めるだろう。
そう思い、ただただ俺はクソガキの攻撃に耐え続けた。非暴力、不服従、まさにガンジーの精神がこの俺に乗り移った様な心境だった。
が次の瞬間……
「ぐはっ!」
股間に超メガトン級の強烈な痛みが走った。クソガキの右ストレートがクリーンヒットする。 俺は思わず自分がサンタクロースだという事を忘れ、着ぐるみから顔を出す。クソガキと目が合う。にっこりと笑って……
「うらぁー、ゴキブリ食わすぞー!!」
脅していた。
「ぎゃあー!!」とか「す、すいませーん!!」とか叫びながら、 全速力で去って行くクソガキと母親。
はぁはぁ……心なしか体が温かくなった様な気がする。気がつくと周りにいた通行人に何かの犯人を見る様な冷たい視線を向けられていた。
俺は「お前達も見てただろ、これは正当防衛だ!」という気持ちを飲み込み、愛想良く会釈をして見せた。我ながらなんて大人な対応なんだと感心して……というかもはや大人でもなんでもない、アホなだけだ。クリスマスに何やってんだろ俺。
紹介するのが遅れたが俺の名前は民谷涼介。こんな感じの高校一年生だ。日雇いバイトの仕事で何だか肌がチクチクしてちょっと変な匂いがするサンタクロースの着ぐるみを着てティッシュを配っている。
デパートの入り口に飾ってある無駄に豪華な装飾が施された時計をちらりと見る。もう午後八時。自分の足下に置かれている段ボールの中身を確認するという行為は、今日一日だけでいつの間にか癖のようになってしまっていた。しかし肝心の中身のティッシュは、なかなか減ってくれない。現に今もどっさりと山のように残っている。しかもまるで体の中から大事な何かが一緒に出ていってしまったんじゃないかと心配になるような長めのため息を吐いていると、全くもって寒さを感じさせない元気ハツラツな声が耳に飛び込んできた。
「すいませーん、よかったらもらってくださーい!」
俺はその声のする駐輪場の方に視線を向けると、同じ日雇いバイトの相棒だと思われるトナカイの着ぐるみを着た人物が、せっせとティッシュを配っていた。あのヒズメでどうやってティッシュを掴んでいるんだろうなんてくだらない事を考えていると、俺と同じように中々の苦戦を強いられているようだった。ティッシュを差し出しては断られ、追いかけては嫌がられ、声をかけては無視される。それは仕事だと割り切っても精神的に気持ちのいいことではない。何もそんなに一生懸命やらなくても……
俺はそんなどこぞやのトナカイ君の不憫な様子を伺いながらふと思う。なんて仕事を引き受けてしまったんだろうと。
そもそも最初はほんの軽いノリだった。高校に入学してもう一年の二学期が終了したってのにツレらしいツレもいない、彼女もいない、そのくせずっと家に居ると親と喧嘩して変にストレスがたまってしまう。だけどクリスマスくらいは、いつもと少し違う事をしてみたいっていうか、割のいいバイトで小遣い稼ぎでも出来ればいいやなんてよからぬ考えが浮かんだ。何がどう転んでそう思ったのか、それとも変な魔が差したのか、今思えば自分でも全く理解のできないその行動は普段の『ザ ・インドアー』な自分からは想像もつかなかった。そんな時、パソコンのインターネットで検索すると日当一万円のバイトが目に入った。職種はイベントスタッフ、詳しい事はあまり書いていないが高校生可という文字を見つけ、自分の条件はクリアしている事に安心した俺は、とりあえず飛び込んでみようという勢いで応募のボタンをクリックしていた。画面にはご応募ありがとうございますの文字。
やっちまった…………本当に勢いというのは恐ろしい。いつもと違う環境に飛び込むという事になかなか慣れてない俺は、日が近づく事にそわそわと心が浮ついてどこか生きた心地がしなかった。自分でまいた種なのにな全く……。
————そしてクリスマス当日。
集合場所のボロくてどこか怪しげな建物にある事務所で仕事内容を聞いた俺は、内心頭を抱える思いで一杯だった。
『サンタの衣装を着て、ティッシュを配る』それが俺に与えられた任務だった。しかしノルマなどは特になく定時になると帰れるらしいが、時間内にできるだけ多く配る事、もし適当に配ってるのがバレたりしたら給料が支払われない事、終わったら事務所に在庫を返す事、これが約束だ。……というかイベントスタッフかこれ? という疑問も担当の強面なおっさんの不気味なぐらい丁寧な仕事説明により言い出すタイミングを打ち消されてしまった。あー変な事したら殺されるんだろうな、という野生の勘みたいなものをビリビリと感じる。そして「にーちゃん、配られねぇからって捨てたりすんのは止めてくれよな?」という脅しの様な言葉にビビりながら「も、もちろんです」という誠意を見せてみたものの、もう後戻りは出来ないという事を俺は悟った。そしてサンタの衣装とポケットティッシュ1000個が入った二つの段ボールを装備し、かくして俺は、戦場であるこのデパートの入り口前にいるという訳だ。
まぁ、なんとかなるだろうと地面にドサッと段ボールを置き準備をし始めた頃はそう思っていた。でも現実は思っている事と同じように物事が動くとは限らない。このデパートの前でティッシュを配り続けてもう八時間が経とうとしていた。ティッシュはなかなか受け取ってもらってもらえない、少し勇気を出して声をかけてみてもちらっと珍しそうに見られるだけだ。特にサラリーマンなんかは鬱陶しそうにして俺の方を見向きもしないで通り過ぎて行く。何度も何度もそれを繰り返した……けれど何度も何度も同じ結果だった。稀に受け取ってくれる人はいるものの、受け取ってもらえない人と比べるとその差は歴然としていた。仕事とはこんなにも過酷なものなのだろうか? こんなにも上手くいかないものなのだろうか? よくよく考えてみると俺は今まで仕事なんてした事はなかった。まぁバイトを禁止している学校もあるみたいだし、俺と同じほとんどの高校一年の奴らからしたらそれが普通なんだろうけど。ただ俺の場合、例の質問達が頭の中で居座っている訳で……
俺のこの冷めた性格はいつからこうなのかわからない。中学の時だって学校が終われば自分はすぐに家に帰って、遅くまで部活や勉強ばかりしてる奴らをどこかで見下していた。何、真剣になってんだよ。暑苦しいんだよって。頑張る事、真剣になる事は格好悪い事だって思っていた。入試もそれとなく受かりそうな高校を受験し入学した。高校に入ってもそんな自分という人間はそのままだった。環境が変わったところでいきなり劇的に何かが変わる訳でもない。特にいじめられる事もなければ、これといって好かれる訳でもない。だから親友と呼べる奴も俺にはいない。自分の周りにいてる奴らは気がついたらつるんでて、ただ時間つぶしに中身のない会話を繰り返しているだけだ。深入りしても結局それが壊れてしまったら何も残らないし意味なんてない。だから俺はこんな感じなのかもしれない。どこかひねくれてて、どんな事でもほどほどの距離を保つのが丁度良い。適当に流されるように生きててもどうにかなる。そりゃそんな奴が急に自分らしくない事をやろうとしたって、昔から染み付いている感覚みたいなものはなくならない。適当に生きてきた人間は、いつまで経っても適当だ。
だから俺はこれからも今まで通りあつくなる事もなく流れに身を任せ続けるんだろう。この仕事だって同じだ。テレビや実際に街で見かけるティッシュ配り。ただティッシュを人に配るだけ。一見、簡単そうで誰にでもできるように思う。けどそう思っている事さえ俺にはろくにできなかった。成り行きはどうであれそれは変わらない事実で、そもそも俺が何かに一生懸命になろうって事自体が無理な話だったんだ。気がつけば辺りは暗くなり入り口前にある時計の針は九時を指していて、地獄の様な仕事時間が終わったという事を告げていた。デパートもシャッターが閉まり、最後の客はポツンと一台だけ駐車場に停まってあった車に乗り込み、エンジンの音を響かせながら去って行った。
——肌寒い風が今の自分の心に追い打ちをかけるように入り込んでくる。
段ボールの中のティッシュはほとんど残ったまま。結局、俺はこの程度だ。何も変わらないしこれが当たり前。俺にとっては当然の結果なのだろう。デパートを後にしようと歩き出した瞬間、俺はとんとんと誰かに肩を叩かれ振り返る。
「お疲れさま」
そこにはさっきのトナカイ君が立っていた。俺のサンタクロースもそうだがデフォルメ化されて愛らしい雰囲気が出ているとはいえ、こうやって間近で見るとなかなか迫力がある。背は俺よりかなり低いみたいだけど。まぁとりあえず一緒にこの戦場をくぐり抜けた同士には違いない。話すのはあまり得意じゃないが少しくらいなら……
「男の人だったんだーっていうか、同い年ぐらいかな?」
トナカイ君はこっちを見ながらそう言った。さっきから聞こえていた元気ハツラツな声の主である事は確かだったが、近くで聞くと声のトーンが思っていた以上に高めで、さらにその発した言葉の内容がキャッチャーに向かってボールを投げたのにいつの間にか自分の後頭部にぶち当たるという恐るべき変化球だった。
男の人? 同い年? じゃあそう言うトナカイ君は一体?
俺の頭の中が大炎上を起こしているのもお構いなしで、目の前のそいつは着ぐるみをすっぽりと脱いでみせた。
「え……」
その瞬間俺は、体の全機能が停止した様に固まってしまった。衝撃的な何かと遭遇すると人間はこんな状態になるのかもしれない。そんな俺の目の前に立っていたのは、トナカイでもなくサンタクロースでもなく宇宙人でも幽霊でもネッシーでもアウストラロピテクスでもなくただの美少女だった。ただのと言っても「二次元からつい出て来ちまったよー」と言わんばかりのすんげークオリティの高いやつだ。
俺の中で勝手にすんげーと位置づけされたその少女は艶やかな髪をバサッと揺らし、着ぐるみを被った時にできた乱れを手グシで整えている。短めに切りそろえられた黒髪と猫のように切れ長で大きな瞳、はにかんだ口元からうっすらと見せる八重歯が妙に色っぽく感じた。っておいおい話が違うじゃないか? てっきり中に入ってるのは筋肉隆々でむさ苦しいおっさんだと思ったら……
——トナカイ君はどうやらトナカイさんだったらしい。
「えっと……その俺十六なんだけど……」
俺は油を注されていないロボットのようなコミュ障っぷりを発揮していた。
「じゃあやっぱ同い年じゃん!そんな君には……はい、あげる!」
突然、目の前にココアを差し出される。
「こ……これは?」
「すっごーく、おいしんだよ」
そして冬の寒さを吹き飛ばして季節ごと変えてしまうんじゃないかと思わせる、真夏のひまわりのような笑顔を向けた。俺は差し出されたココアをサンタの手袋越しに受け取りほっとする。まだ温かい。仕事が終わって近くの自販機で買ったんだろうかなんて考えながらココアを眺めているとやたらと派手なラベルが目に飛び込んできた。
(どすこいココア)
なんつー名前だ。そこには巨漢の力士が張り手を繰り出しているイラストが描かれていた。見るからに暑苦しい。本当にすっごーくおいしいんだろうか? 不安になってくる……まぁせっかく奢ってくれたんだし目の前のこの子に申し訳ないという気持ちもあって、とりあえず飲んでみる事にした。
どすこい……どすこい…………どすこい………………………………あ、意外といける。
意味不明な呪文を心の中で復唱し、もしもの時のために精神を落ち着かせていたが予想を大きく裏切ってなかなかの美味だった。俺が満足そうな表情をしていると、彼女もさらに笑顔になって
「でしょー」
と、あたかも自分が製造している張本人のように誇らしげに言った。夜のデパート前。あたりにはほとんど人の気配はなく、遠くからうっすらと車の走っている音なんかが聞こえるぐらいで、今から何時間前かのあの騒がしさは一体何だったのだろうと思ってしまう静けさだった。どすこいココアを飲んでくつろいでいるサンタとトナカイ。変な状況だ。ちょこんと建物の壁にもたれて満足そうにコーヒーを飲んでいる少女。トナカイの着ぐるみから顔を出しているため、ただのコスプレのように錯覚してしまう。俺はふと気になった事があったので聞いてみた。
「……あのさぁ君、結局ティッシュ配れたの?」
彼女は自分の後ろに置いてあった段ボールの中身を俺に見せる。俺は目を疑ってしまった。そこには俺と大して変わらない量のティッシュが山を作っていた。そんな……なんで……
「ぜーんぜん。みんなちっとももらってくれなかったよ」
それでも彼女は笑顔だった。何でそんなに笑顔でいれるんだろう……俺が配れなかった理由はわかっている、途中からいつもみたいに適当になって投げ出したからだ。けど……彼女は違う、見る限りずっと一生懸命頑張っていた……
「ティッシュ配り難しいねー、思ってたよりもずっと大変だったな」
俺は黙って彼女の言葉を聞いていた。そして気がつけばいつものように皮肉や時間を埋める為の言葉ではなく、素直に感じた言葉が自分の口から出ていた。
「……でも君すごいよな、全然あきらめないで。何度も声かけにいってさ……」
「そんな事ないよ」
「俺なんか何回も無視されて、クソガキには殴られて、そのたびに心挫けそうっていうか……こりゃ真面目にやっても意味ねーなって感じで……」
「そうだね…………けどこんな経験なかなかできる事じゃないし、あたしはすっごく楽しかったな」
「……」
俺には彼女の言っている事が理解できなかった。……だから戸惑った。
「なんで……なんでそんなに頑張るんだ? あの感じだったらある程度適当にやってても大丈夫だよ。別に見張られてる感じでもなかったし、給料だって払ってくれるって!」
俺は興奮して声を荒げていた。息が乱れて、どこか怯えて、まるで自分という存在がかき乱されていくような感覚だった。
「……あっ、もうこんな時間だよ、そろそろ事務所もどろ」
彼女は相変わらずの笑顔を俺に向けてそう言った。結局その質問に対する答えを聞く事は出来なかった。どこかぎくしゃくした雰囲気のまま二人して事務所に向かったのはいいが、二人とも段ボールの中身をほとんど配れていないという惨敗っぷりだったので例のおっさんに殺されるのではないかという不安が、事務所に向かうまでの一歩を鉄球でつながれているように重くしていた。しかし人は見た目によらなかったみたいで、おっさんは返却されたティッシュの山をみつめながら意外にも気さくな態度で。
「まぁ初めてだからしゃーねぇな、次またここに来る機会があったらもうちょっと頑張ってくれよ」
と、言って封筒に入った一万円札を俺たち二人に手渡してくれた。俺は一万円札入りの封筒を手に持ち思い詰めた顔をしていると、彼女が隣でサンタから私服に着替えたばかりの俺のダウンジャケットの裾をクイクイと引っ張っていた。俺は彼女を見てうんと頷き二人で「ありがとうございました」とおっさんに頭を下げた。
「遅くまでご苦労さん」
そして、にこっと笑って送り返してくれた。実はいい人だったんだな。俺たちはおっさんの笑顔に感謝をしながら事務所を後にした。外に出る頃にはもう夜の十時を過ぎていた。吹き続けている風もいつの間にかさらに寒さを増しているように感じる。俺は事務所の前に停めてあった今にも変形しそうなおんぼろオレンジチャリの鍵をカチャリと開けて道路の前まで引っ張りだし、よっこらせと勢いよく股がった。がその瞬間、肩に何かの感触とチャリの後部にわずかな重さを感じた。
「よし、レッツゴー」
振り返ると彼女が手を振りかざし、今から探検に出かける冒険家のような好奇心に満ちあふれた表情を浮かべていた。俺の肩に手をかけ、チャリに取り付けられた棒に足を乗せてバランスをとっている。ちょっとまて、一度この状況を整理してみよう。夜中に男のチャリに女が乗って走り出す。こ、これは……もしかして……よく映画やドラマやアニメや漫画やラノベやギャルゲーで鉄板中の鉄板。夢にまで見たチャリ二人乗りというやつではないのか!!!!!
「ねぇーいいでしょ」
俺はとっさにありとあらゆる場所をつねってみたが全て痛かった。うん、夢じゃない。
「どすこいココアおごってあげたしさ。だーかーら家まで送ってー」
「うおぉー!!! お安い御用だぁぁー!!!」
俺はペダルを踏み込む足に、女っ気が皆無だった十六年の切実な思いを込めて夜の街を爆走していった。
◆◆◆
住宅街やスーパーを通り過ぎながら、心臓が大音量で悲鳴を上げていた。原因はと言うと元から体力がないのも多少はあるだろうが、それ以上に精神的な部分が多くを占めていたと思われる。透き通るような話し声は耳元の近くで聞こえてゾクッとするし、たまに道がデコボコしてお互いの体が密着する時は直に彼女の体温を感じてしまうし、つい鼻に入ってくる一体どこから放出されているんだという彼女の謎の良い香りの前では冷静や平常心という言葉で対抗するなど到底無理な話で俺は、いつの間にか目眩がするのを必死で堪えるという謎の戦いを繰り広げていた。おかげで道中、何を話したんだかさっぱり覚えてない……
「着いたー!」
「あっち」とか「こっち」とか後ろから聞こえてくる声に従ってチャリを走らせていると、家と呼ぶにはほど遠い緑に囲まれた小さな丘のような場所に辿り着いていた。
彼女はチャリから下りると、一目散に駆けて行って自分の納得いく位置で足を止めていた。
上は温かそうな上品で茶色のコートだったが、下はチェックの赤いミニスカートに黒のニーハイという見るからに寒そうな格好だ。けれどあのはしゃぎようからして、彼女にはそんな事は大してどうでもいいみたいだった。俺もゆっくりと彼女の隣に近づくと、突然飛び込んでくる光景に目を奪われていた。圧巻というのはこういう事を言うのだろう。
目の前に広がっていたのは、自分は今どこに立っているのかわからなくなってしまいそうな、夜の街の姿だった。近くで見る街のネオンにはあまりいい印象はなかったが、こうやって角度を変えて見てみるとどこか別の場所のように綺麗で幻想的だった。
「いいでしょ? ここはこの街が一望できるんだ」
「あぁ、すごい……」
————お互い黙った時間がどれだけ続いていたのか、先に静寂を破ったのは彼女だった。
「ね、さっきの話」
「ん?」
「とぼけないでよ。何でそんなにお前は頑張るんだって言ってたよね?」
「あぁ……」
「……別に頑張ってるつもりなんてないんだよ、あたし」
彼女は真っすぐ前を見つめたまま、静かにそうつぶやいた。
「わからない……俺の目から見れば君は精一杯頑張ってた。大慌てで走り回って、無視されても通行人に声かけて、なのにあのティッシュ配りの成果だって適当にやってた俺とあんまり変わんなかったんだ。それでも君は何事もなかったみたいに笑顔で、前向きで…………」
「……」
「一生懸命やってもまた結果が出ないかもしれない、深く入り込んだせいで大事な何かが壊れてしまうかもしれない、下手したら自分が傷つく事だってある……君は…………怖くないのかよ?」
俺は初めて自分以外の誰かにずっと思い続けていた疑問をぶつけていた。彼女は俺の方を向いて少し笑いながらも、けど真剣な眼差しで、
「怖いよ……けど何にもないのが一番怖いって思うから……」
「え?」
「あたしさもともと体が弱くて、中学に入学してからずっと入院してた事があったんだ。……みんなが文化祭で一生懸命になってる時も、修学旅行で楽しんでる時も、自分はずっと病院のベッドの中でただ窓から外を眺めてた。それで想像するんだ。今日はこんな楽しい事があったんだろうなぁとか、こんな大変な事があったんだろうなぁとか。けどそんな想像だけじゃ何にも変わんなくて、やっと体調が落ち着いて退院した頃にはびっくりするぐらいの時間が流れてた。久しぶりに入った教室にはもう自分の居場所なんてなくて、みんなの中にある思い出をあたしは持ってないんだって……病院にいる間、大事な何かを落っことしちゃったんだって……ぽっかり心に穴が開いたみたいだった。結局、ちゃんと教室で過ごしたのはほんの数ヶ月で卒業式で証書をもらった時あたし思ったんだ……」
彼女は唇を噛み締め、そしてゆっくりと続けた。
「全然……重くないなって……」
どこか泣いているように思えた。
「その手に持った紙は本当に軽くて、あたしの思い出なんかちっとも詰まってなかったんだよ……」
風がひゅるりと吹いて、彼女の前髪を揺らしていた。俺はそんな彼女を黙って見つめてい。
少しずつ何かがつながっていくような気がした。彼女が今まで何を抱えていたのか、何を抱えて生きようとしているのか。
「だから……だからさもう失いたくないんだよ。あたしはね、今の時間を精一杯楽しむんだ。楽しい事も悲しい事も全部楽しむの。だってそれはただ外から眺めているだけでは出来ない事だから。どんな結果になってもいい、脇役でもいい、自分の舞台にちゃんと立っていたいんだ」
彼女はそう言って、とびきりの笑顔を俺に見せていた。……自分がちっぽけに思えた。情けなくて、惨めで、自分が考えていた事なんてただの弱音ばかりで。最初から何もかもあきらめて、傷つく事から逃げ続けている俺には、彼女の言う何もない怖さなんてこれっぽっちも理解できなかったんだ。それなのに自分は違うんだって周りを見下して、いい気になって、一番格好悪いのは俺じゃないか。……本当はわかっていた、そんな自分の弱さも、情けなさも全部。けれどそれを受け止めてしまったら何もかも崩れさってしまうんじゃないかって、もう自分が自分でいられなくなってしまうんじゃないかって、それが怖くて怖くて仕方がなかった……だから帰りの道中も後ろでずっと黙ったままの彼女に対して、俺は何も声をかけられなかった。自分の自宅付近に辿り着いた彼女はよっとチャリから下りて、
「今日はほんとにありがと。また……また会おうね!」
と言葉を残していた。一歩、また一歩とアスファルトを踏みしめて前に進みながら。
その小柄で触れたら壊れてしまうんじゃないかという後ろ姿が、どこまでも強くて、どこまでも芯があるように思えた。もし今日、自分が日雇いバイトをしていなかったら? もし今日、彼女と出会っていなかったら? そう考えると胸の中がもやもやして、俺に良い言葉なんてかけられる訳ないけど、何も意味なんてないのかもしれないけれど、遠ざかって行く彼女に向かって何かを自分の心に刻み付けるみたいに、
「あの……俺、田宮涼介!」
とだけ言っていた。そして、
「……あたしは宮沢弥生だよ」
振り返った彼女はそう言い、俺は再び遠ざかって小さくなってく姿をいつまでも眺めていた。時計を見るともう十二時を回っていた。時間が過ぎる、日が変わる、それは今日という日がもう二度と戻って来ない、リセットされてしまったという事実だった。宮沢弥生……変わった女の子だった。俺とはまるで正反対のように思えた。俺の頭の中でぐるぐると回り続けていた言葉。
「何かを真剣にやってきた事はあったのだろうか?」
「壁にぶちあたった事はあったのだろうか?」彼女はそれがしたくても出来なかった。俺みたいに臆病になって最初から逃げたりはしなかった。むしろそれに立ち向かっていた。そんな彼女は格好悪いだろうか? 俺に彼女を否定する事なんてできるのだろうか? いいや、そんな事できるわけない。彼女は彼女の道を歩いてるんだ。……彼女の? じゃあ俺にとっての道とは一体なんだ? …………俺は強くなりたい。男だとか女だとかそんなの関係なく、一人の人間として彼女のように強くなりたい。
そんな事が俺にもできるだろうか? 今の自分の殻を破って、変われる事ができるんだろうか?
何かに一生懸命になって、向き合って、良い事も悪い事も全部自分で受け止める。それは他の誰でもない自分の責任だ。今はまだわからない、こんな臆病な自分がすぐに変わるという保証なんてない。けれど一つだけ確かな事がある。俺は鞄の中から今日もらった封筒を取り出していた。中途半端だったかもしれない、上手く行かなかったかもしれない、けれどこの手には確かにずっしりとのしかかる重さが存在している。今日自分が体験した事、感じた事、そして彼女との出会いに対する重さが。クリスマスは誰でも平等に贈り物を貰える日。彼女が帰って行った方向とは逆の道を進みながら、俺は自分のちっぽけさと今日という日にもらった贈り物の重さを一人噛み締めていた。
完
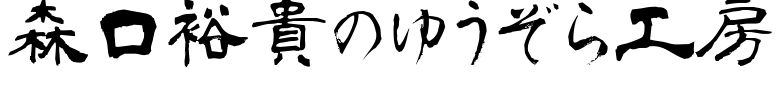

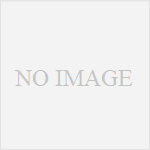
コメント